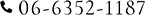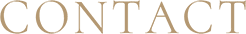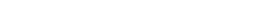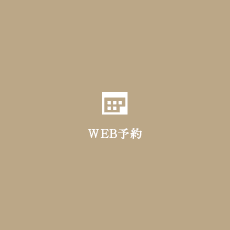【普段の食事で歯周病を防ぐ!】歯や歯茎と食生活の、意外な関係
こんにちは。
大阪市北区 東天満 地下鉄南森町駅・JR大阪天満宮駅からすぐにある 増田歯科・矯正歯科です。

「最近、歯ぐきが腫れている気がする…」
「歯を磨くと血が出る…これって大丈夫?」
そんな不安を感じたことはありませんか?
実はそれ、「歯周病」のサインかもしれません。
そしてその歯周病、実は“食生活”とも深く関係しているってご存じでしたか?
今回は、歯周病と食生活の関係性と、歯や歯茎を守る食事について詳しく解説します。
目次
1,甘いものだけが悪いわけじゃない?

歯周病といえば「磨き残し」や「細菌」が原因と思われがちですが、毎日の食事内容や栄養バランスも、実は歯ぐきの健康に大きく影響を与えているんです。
たとえば…
▸ ビタミン不足 → 歯ぐきの修復力が落ちる
特にビタミンCは、歯ぐきの土台となる「コラーゲン」の合成に欠かせません。
不足すると、出血しやすくなったり、歯ぐきの腫れがなかなか引かなかったりします。
歯周病じゃないのに歯茎に元気がない…という場合は、ビタミンCが不足しているのかも。
▸ 加工食品や糖質の摂りすぎ → 炎症を悪化させる
パンやお菓子、スナック菓子などの加工食品には、糖質や酸化しやすい脂質が多く含まれています。
これらは体の「慢性炎症」を助長し、歯ぐきの炎症を長引かせる要因に。
▸ たんぱく質不足 → 免疫力が落ちて歯周病菌に負けやすくなる
免疫細胞や組織を作る材料であるたんぱく質が不足すると、体が細菌と戦えず、歯周病菌の繁殖を許してしまいます。
このように、どんなに日ごろ歯みがきを頑張っていても、身体の中からのケアができていなければ、歯周病は根本的に改善しにくく再発もしやすくなるのです。
2,歯ぐきを守る!食生活のヒント

では、歯ぐきの健康を守るにはどうしたら良いのでしょうか?
今日から取り入れられる、簡単な食生活のポイントをご紹介します。
ビタミンC(柑橘類、ブロッコリー、キウイなど)
→ ビタミンCは、歯ぐきの結合組織を強く保つために重要です。
さらに、血管を丈夫にして「出血しにくい歯ぐき」づくりをサポートしてくれます。
オメガ3脂肪酸(青魚、亜麻仁油、えごま油など)
→ サバやイワシに含まれるオメガ3系脂肪酸には、炎症を抑える作用があります。
歯周ポケット内の炎症性物質を減らす効果が研究でも示されています。
良質なたんぱく質(魚・肉・卵・豆腐・納豆など)
→ 傷ついた歯ぐきを修復し、免疫機能を維持するにはたんぱく質が不可欠。
とくに、高齢者やダイエット中の方は不足しがちなので意識的に摂りましょう。
★加工食品・甘いお菓子は「量と頻度」に注意!
→ 糖質を摂るな、ではなく「ダラダラ食べないこと」がポイント。
ちょこちょこ食べていると、口の中がずっと酸性に傾き、歯周病菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。
3,「グリセミックロード」にも注目を
また最近では、「糖質の質と量」が健康に与える影響として、グリセミックロード(GL)という指標が注目されています。

▶ グリセミックロード(GL)とは?
GLは「食品が血糖値にどれだけ影響するか」を表すもので、グリセミックインデックス(GI)×炭水化物量で計算されます。
つまり、同じGI値でも食べる量によって体への影響が大きく変わるということ。
▶ GL値が高いとどうなる?
GL値が高い食品(例:白パン、ケーキ、清涼飲料水など)を頻繁に摂ると、血糖値が急上昇 → インスリンの過剰分泌 → 炎症促進 という悪循環に。
これは歯ぐきの炎症にもつながるため、GLの低い食品(玄米、野菜、豆類など)を意識して選ぶことが歯周病予防にも効果的です。
4,歯ぐきから始まる、全身の健康

歯周病は自覚症状が少ないため、気づいたときには進行していたというケースも少なくありません。
さらに、以下のような全身の病気とも深い関わりがあることが分かっています。
-
糖尿病
-
動脈硬化
-
心筋梗塞・脳梗塞
-
認知症
-
早産・低体重児出産
つまり、歯ぐきの健康を守ること=全身の健康を守ることでもあるのです。
~まとめ~
お口の健康は、体の健康の入り口
歯周病は自覚症状が少ないため、「気づいたときにはかなり進行していた」というケースも珍しくありません。
さらに、糖尿病や動脈硬化、早産・低体重児出産など全身の病気とも関係が深いことがわかってきています。
「最近、歯ぐきが気になるな…」
「ちゃんと磨いているのに、歯ぐきの調子が悪い…」
そんな方は、ぜひ一度歯周病チェックを受けてみてください。
当院では、お口のケア+食生活アドバイスの両面から、皆さまの健康をサポートしています。

【あわせて読みたい】
🦷歯茎の出血や歯周病についてさらに詳しく知りたい方はこちら
ご予約はこちらから
お電話(0663521187)でも承ります!
【監修】

歯科医師/医療法人健誠会 増田歯科・矯正歯科 理事長・院長
大阪市北区・南森町で歯科医療に従事し、成人矯正・小児矯正・インプラント・審美歯科・予防歯科まで幅広く対応。インビザラインプラチナプロバイダーとしての豊富な症例実績をもち、国際口腔インプラント学会認定医や咬み合わせ認定医として専門性の高い診療を行っています。